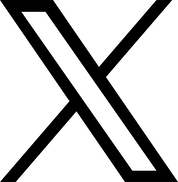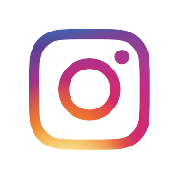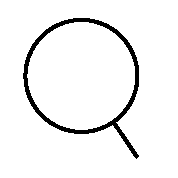映画『アステロイド・シティ』ウェス・アンダーソンにインタビュー“フィクションを作る過程を描いてみたい”
映画『アステロイド・シティ』の監督・脚本を務めたウェス・アンダーソンにインタビュー。
ウェス・アンダーソン監督にインタビュー

『グランド・ブダペスト・ホテル』や『犬ヶ島』など唯一無二の世界観を楽しめる映画を世に送り出し、世界中の人々を魅了し続ける監督、ウェス・アンダーソン。そんな彼が贈る最新作は、1950年代のアメリカを舞台とした映画『アステロイド・シティ』だ。
『アステロイド・シティ』では、2つの物語が同時進行で展開される。1つはアメリカ南西部に位置する架空の砂漠の街、アステロイド・シティを舞台にした新作劇。もう1つは、その新作劇の舞台裏に密着したテレビ番組だ。新作劇ではアステロイド・シティで起きた一つの事件にまつわる群像劇が展開され、テレビ番組では新作劇の創作過程が描かれる。そんなユニークな構成の物語はどのようにして生まれたのか?公開に先駆けてインタビューを実施した。
2つの要素を落とし込んだ映画

『アステロイド・シティ』は、新作劇とテレビ番組という2つの世界を行き来しながら物語が進行していきます。このアイデアはどのようにして生まれたのでしょう?
実は、最初から二つの世界をまたぐ、入れ子構造の映画にしようと思っていたわけではありません。もともと僕には、舞台劇が完成するまでの制作過程を描きたいという思いと、砂漠を舞台にしたストーリーを作りたいという思いがあり。別々の作品を作っても良かったのですが、最終的に2つの要素を1つの映画に入れ込むことで、自然とこのような形になりました。
着想源となった作品はありますか?
入れ子構造的な要素ではあまり思いつきませんが、それ以外の部分では色んな作品からインスピレーションを得ています。特に影響を受けたのは、ニューヨークの舞台で活躍した人たちが関わる作品です。
例えば、劇作家サム・シェパードのエッセイ『モーテル・クロニクルズ』を原作としたヴィム・ヴェンダース監督の映画『パリ、テキサス』。『アステロイド・シティ』の舞台になった1950年代の作品ではなく1980年代の作品ですが、制作過程で頭に浮かんできました。
また、アリゾナの砂漠が登場する1936年公開の『化石の森』や、フリッツ・ラング監督でスペンサー・トレイシーが出演する獄中を舞台にした『激怒』、ロバート・ライアン主演の砂漠を舞台にした3D映画『地獄の対決』、世界的に有名な劇作家アーサー・ミラーが脚本を手掛けた、マリリン・モンローやモンゴメリー・クリフトが出演するジョン・ヒューストン監督の『荒馬と女』。
あるいは、シドニー・ルメット監督の『女優志願』。これはマリリン・モンローの演技指導をしていたアクターズ・スタジオの女性、ポーラ・ストラスバーグを母親に持つスーザン・ストラスバーグが出演している映画です。『アステロイド・シティ』にはマリリン・モンローのような女優が登場しますが、そういった作品からもインスピレーションを得ました。

監督は以前のインタビューで、身近な人を作品のキャラクターとして描くことが多いとおっしゃられていました。今回も身近な人をモチーフにしたのでしょうか?
このキャラクターはこの人をベースにしていますというのは、『アステロイド・シティ』ではあまり無いですね。今回は役者や作家についてのお話、演技をすること、作品を作ることについての映画にしようと考えていたので。ではそれは何に基づくのか?といえば一種の関わってきた俳優たちへの興味です。
僕は長年、監督として作品を作り、脚本を書いてきたものですから、いろんな役者とお付き合いしてきました。そして、彼らはとっても興味深い。だから、ここに出てくる色んなキャラクターたちは、僕がこれまで交流してきた数多くの役者たちがベースになっています。
例えば、ジェイソン・シュワルツマンが演じた父親のオーギーと役者のジョーンズの2役は、本人とは大分かけ離れたキャラクターではありますが、彼のために書き下ろした役なので色んな要素を活用させてもらいました。
オーギーの娘たちも、とてもチャーミングで印象的でした。
そうですね。僕には7歳の娘がいるのですが、彼女がいなければあのような娘たちを登場させることはなかったと思います。
フィクションを作る過程をリアリティーとして描いてみたい

前作の『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』では“架空の街”の編集部の物語が描かれ、今回も“架空のドラマです”という断りが入っています。「架空(フィクション)」という言葉を使った意図はあったのでしょうか?
実はこの映画を見た友人からも同じようなことを聞かれました。あえて「フィクションです」と言うことによって、観客と作品の間の距離感を保ちたいのか?と。でも、僕自身は全然そんなことを望んでいるわけではありませんでした。
別の意図があったんですね。
『アステロイド・シティ』では、フィクションを作る過程を1つのリアリティーとして描いてみたいと思いました。先にもあげましたが、今回描こうと思ったのは作家たちや役者たち。彼らがどのように物語を紡ぎ、どのように生み出していくのかという“創造の過程”を見ることがたまらなく面白いと感じるんです。物語はこういうギミックを使ってこういう風に作り上げるのだということを表現してみたいという思いがありました。

舞台裏をあえて見せる、と。
そうです。僕の場合、こういう効果を狙って鏡を使っているんだとか、舞台裏のギミックが分かった方がむしろ興味を引かれるんですよね。その最たるものがジャン・コクトーの作品です。
例えば『美女と野獣』。信じられないかもしれませんが、コクトーの『美女と野獣』ではお城のキャンドルを人の手が持っていて、あえてそれを見せているんですよ。鏡を使って見せるシーンもあって、それがまた面白いと感じますし、フィルムを逆に回している(※)ことがあからさまに分かるシーンもある。そのようなギミックが分かるからこそ面白さが増していくというのが僕の感覚です。
決して自分をコクトーと比較するつもりはありませんが、創造の過程や趣向を凝らしたギミックがたまらなく面白いと感じるので、創造の過程、そこに託された巧みを見せてみたい。あえて「架空」という言葉を使ってフィクションを作る過程を描いたんだと思います。
※フィルムを巻き戻すことで、映像が元に戻る表現。今で言うと逆再生すること。

そんなフィクションを作る過程を描いた『アステロイド・シティ』では、大切な人を失うという悲しみと向き合う家族も描かれています。監督がそこに込めたメッセージとは何でしょう?
特別に何かを語りたかったわけではありませんが、『アステロイド・シティ』の物語を作る時は、この世を去ってしまった人たちに思いを馳せていたのだと思います。
と言うのも、僕自身54歳にもなると多くの死別を経験してしまうんですよね。身近な人との死別は、辛い精神状態を引っ張りながら、悲しい思いの中で過ごさなければなりません。大切な人への想いの日々を泳ぐことになりますよね。『アステロイド・シティ』では、そのような心持ちがジェイソン・シュワルツマンの一家にまつわる物語に反映されたのではないかなと思います。
複数の視点、巧が重なることで生まれる独自性 - その人しか描けないもの

ウェス・アンダーソン作品は、これまで多くの観客たちを魅了してきましたね。一方、監督ご自身が最近観た映画の中で 、理想の作品、心を鷲掴みにされた作品はありますか?
理想の映画っていうのは、その時々で変わります。これぞ史上最高の作品!みたいなことを感じても、それは変わっていくものです。
ちょうど昨晩、半分寝ぼけながら鑑賞していたのですが、エミール・ゾラの小説を原作としたジャン・ルノワール監督の映画『獣人』は、改めて素晴らしい作品だなと思いました。実は約30年程前にも観た作品だったのですが、“どうしてこれまで繰り返し見てこなかったのだろう”と、すっかりこの作品を忘れていたことに後悔を覚えたほどです。

一体『獣人』のどんな要素に、そこまで心惹かれたのでしょう?
『獣人』は1938年公開の映画で、1800年代後半のフランスの全てを出来る限り忠実に、写実的に描こうとしたエミール・ゾラによる『ルーゴン=マッカール叢書』の1編を映画化したものです。舞台は蒸気機関車なのですが、その中で働く「ショファ(chauffeur)」のお話が描かれています。
ショファは英訳すると運転手ですが、語源のフランス語は運転手ではなくて蒸気機関車に石炭をくべる人たち。劇中では、彼らの様子がドキュメンタリータッチで物凄くリアルに捉えられています。『獣人』のカメラワークはジャン・ルノワールならではで、石炭をシャベルでくべる様子が生き生きと映されている。それがものすごくダイナミックで、蒸気機関車ってこうやって走るんだというのを強く感じさせるんですよね。
一方、役者も演技にかける巧が光っていて。ジャン・ギャバンやシモーヌ・シモンたちが出演していますが、彼らが演じなければ見られなかった演技の視点がある。ジャン・ルノワールの巧みはどういうところにあるのかっていうと、役者のキャスティングの才能が光っているのと、そういうキャストたちに対してどういう演出を仕掛けるのかっていうところだと感じるんです。
でもそれでいながら描かれているのは、ある男が別の男の妻に横恋慕するという三角関係で、ジャン・ルノワール監督ならではのフィルム・ノワール(※)になっていて。そしてさらに、ほのかな喜悲劇としても描かれているんですよね。
※フランス語で「暗黒映画」の意味を持つが、1940年〜1950年代にかけてハリウッドで盛んに作られていた犯罪映画を指す。
ピックアップ


スケジュール



![fashionpress[ファッションプレス]](/img/common/logo_0119_1928.svg)