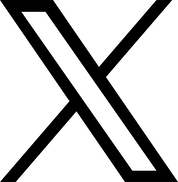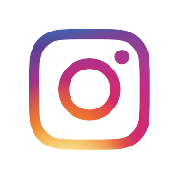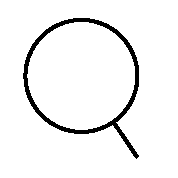M A S U 2026年春夏コレクション - 衣服が紡ぐ生の時間
M A S U(エム エー エス ユー)の2026年春夏コレクションが発表された。
システムの透明性に抗して

「2026年春夏は、計算され尽くした世界、言わば、予定調和に対する最後の反逆である」──「in the raw」と題された今季のM A S Uには、こんな言葉が寄せられている。「計算され尽くした世界」、それは、対象を合理的・経済的に扱うべく、物ばかりか人、その内面をも数量化し、画一的にモデル化し、そのシステムに従って予測を行う、近代的な世界であるといえよう。そこで数量的な体系にそぐわぬ要素は、ことごとく零れ落ちることになる。

M A S Uのデザイナー後藤愼平は、そうしたもの作りのあり方に対して、それを「愛せるのだろうか?」と問いかける。後藤にとってファッションの魅力とは、生の体験であり、出会いであり、偶然であるのだ。それならば今季のテーマにある「raw=生(なま)」とは、数量化によって捉えられる手前にある生の世界、あるいは合理的なシステムから外れるアノマリーの領域を指し示す言葉ではなくて何であろう。

今季のM A S Uには、だから、システムの冷ややかさに抗うブリコラージュ的な身振り、あるいは全き完璧さをシニカルに笑う綻びを、随所に見てとることができる。たとえば、結束バンド。ピークドラペルのテーラードジャケット、フロントファスナーのフーディ、デニムパンツなどは、衣服を構成する複数のパーツが、無数の結束バンドで繋ぎとめられている。これら、着る人が自ら繋げることでできあがる衣服には、あらかじめ予期されていなかった組み合わせの偶然性、そして自ら衣服を組み立てる身振りという、生の感覚が色濃く反映されているといえよう。

あるいは、衣服に蠢くかのような綻びの数々。Vネックニットやキルトスカート風のボトムスのワンポイント刺繍は文字どおり綻びを見せ、チノパンのベルトループは捩れ、ボーダーTシャツは裏表が反転したかのように縫代を外側に出す。また、ショートパンツなどでは、ストライプ柄のライニングがはみ出て立体感を生みだし、Tシャツのミスプリントが予期せぬ表情を示すなど、「きちんとした」衣服に綻びを導きいれている。

こうした綻びは、ヴィンテージ感を帯びたような素材にも当てはまる。ダメージ加工を施したデニムパンツは、遠目にもわかりやすい例だ。あるいは、ボンバージャケットは色褪せたような風合いで仕上げ、ジャケットやシャツ、ショートパンツには、くたっと柔らかさを帯びたベロアを用いる。さらに、通常であれば整った肌理が求められるテーラードジャケットも、毛玉を帯びたウールで仕立てるなど、経年変化を彷彿とさせずにおかない。人が身に纏い、その動きに合わせて馴染み、擦れてゆく時間の経過──そこに、合理性のシステムが予測する透明な時間とは異質な、生の時間を読み取ってもよいのかもしれない。
ピックアップ



スケジュール



![fashionpress[ファッションプレス]](/img/common/logo_0119_1928.svg)